ハクビシンの侵入を防ぐ隙間対策は?【4cm以下に封鎖が有効】効果的な材料と施工方法を詳しく解説


【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの侵入に悩まされていませんか?- ハクビシンはわずか4cmの隙間から侵入可能
- 屋根裏や壁の見落としやすい箇所を重点的にチェック
- 金属メッシュや発泡ウレタンが効果的な封鎖材料
- 季節による建材の膨張収縮に注意が必要
- DIYで簡単に実施できる革新的な対策方法
- 定期的な点検で再侵入リスクを最小限に
実は、わずか4cmの隙間からでも忍び込んでくるんです。
「えっ、そんな小さな隙間から!?」と驚かれるかもしれません。
でも、大丈夫。
この記事では、誰でも簡単にできる隙間対策をご紹介します。
金属メッシュや発泡ウレタンを使った効果的な封鎖方法から、意外な日用品を使った裏技まで。
あなたの家を「ハクビシン要塞」に変身させましょう。
さあ、安心して眠れる夜を取り戻す準備、始めましょう!
【もくじ】
ハクビシンの侵入を防ぐ隙間対策の重要性

ハクビシンが通れる隙間は「わずか4cm」の衝撃!
驚くべきことに、ハクビシンは直径わずか4cmの隙間があれば侵入できてしまうのです。「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と思われるかもしれません。
でも、本当なんです。
ハクビシンの体は意外と柔らかく、頭が通れば体も通れるんです。
まるでゴムのように体をくねくねさせて、小さな隙間をすり抜けていくんですよ。
「そんな、うちには4cmもの隙間なんてないはず…」なんて思っていませんか?
実は、家の至る所に侵入口となりうる隙間が潜んでいるんです。
例えば:
- 屋根の軒下の隙間
- 換気口のすき間
- 外壁のひび割れ
- 配管の周りの穴
- 古い窓枠の隙間
「ちょっと待って、うちの家も危ないかも…」そう思った方、要注意です!
ハクビシンは夜行性で、人間が寝静まった夜中にコソコソと活動します。
そして、一度侵入ルートを見つけると、そこを何度も利用するんです。
つまり、小さな隙間を放置しておくと、ハクビシンの常連さんになっちゃうかもしれません。
だからこそ、4cm以下の隙間をしっかりと塞ぐことが大切なんです。
「よし、今すぐに家中の隙間をチェックしよう!」そんな気持ちになりましたか?
次は、具体的な対策方法を見ていきましょう。
見落としがちな「侵入経路」チェックリスト
ハクビシンの侵入経路は意外なところにあります。普段気にしない場所こそ要注意なんです。
「えっ、そんなところから入ってくるの?」と驚くかもしれません。
でも、ハクビシンは私たちの想像以上に器用なんです。
まずは、よくある侵入経路をチェックリストにしてみましょう。
- 屋根裏の換気口:風通しのために開けた穴が、思わぬ侵入口に
- 軒下の隙間:屋根と外壁の間の小さな隙間も見逃せません
- 雨どいのつなぎ目:排水パイプの接続部分が緩んでいることも
- 外壁のひび割れ:年月とともに生じた小さな亀裂も侵入の糸口に
- 窓枠や戸袋の隙間:古い建具ほど隙間ができやすいので要注意
- 配管周りの穴:水道管やガス管の周りの隙間も忘れずに
実は、多くの家庭でこれらの侵入経路を見落としているんです。
特に注意が必要なのは、築年数の古い家です。
年月とともに建材が劣化し、知らず知らずのうちに隙間が広がっていることがあります。
「ガタガタ」「ミシミシ」といった音が聞こえたら要注意です。
また、季節の変化も侵入経路を作り出す原因になります。
夏の暑さで建材が膨張し、冬の寒さで収縮することで、微妙な隙間ができてしまうんです。
「そういえば、寒くなると窓の閉まりが悪くなるなぁ」なんて経験ありませんか?
定期的なチェックが大切です。
「でも、どうやってチェックすればいいの?」と思った方、ご安心ください。
次は、プロ顔負けの隙間発見テクニックをご紹介しますね。
隙間を放置すると「被害拡大」の危険性大
ハクビシンの侵入を許してしまうと、思わぬ被害が待っています。「まぁ、たまに入ってくるくらいなら大丈夫かな」なんて甘く考えていませんか?
実は、放置すると事態はどんどん悪化していくんです。
まず、ハクビシンが家に住み着いてしまう危険性があります。
彼らにとって、人間の家は絶好の隠れ家なんです。
暖かくて、雨風をしのげて、おまけに食べ物まであるなんて、ハクビシンにとっては天国みたいなものです。
そして、一度住み着くと次々と問題が発生します。
例えば:
- 天井裏や壁の中で糞尿をする
- 電線やケーブルをかじる
- 断熱材を巣材として使用し、破壊する
- 騒音で夜眠れなくなる
- 寄生虫や病気を持ち込む
これらの被害は、時間とともにどんどん深刻化していくんです。
特に怖いのが、衛生面での被害です。
ハクビシンの糞尿には様々な病原菌が含まれています。
これが原因で、家族の健康に悪影響を及ぼす可能性があるんです。
「子供やペットのことを考えると心配だなぁ」そんな不安も当然です。
さらに、家屋への損傷も見逃せません。
電線をかじられて火災の危険が高まったり、断熱材を破壊されて冷暖房効率が落ちたりと、住環境にも大きな影響が出てしまいます。
「修理費用もバカにならないよね…」そう、放置すればするほど、対策にかかる費用も膨らんでいくんです。
早めの対策が、被害拡大を防ぐ鍵となります。
では、具体的にどんな対策が効果的なのでしょうか?
次は、そのポイントを詳しく見ていきましょう。
「目視だけでは不十分」隙間発見の裏技とは
ハクビシンの侵入口を見つけるのは、思った以上に難しいものです。「目で見て回ればいいんでしょ?」そう思った方、ちょっと待ってください。
実は、目視だけでは見落としてしまう隙間がたくさんあるんです。
そこで、プロ顔負けの隙間発見テクニックをご紹介します。
これらの方法を使えば、今まで気づかなかった侵入口も見つけられるはずです。
- 光漏れチェック法:夜間に室内の電気を全て消し、外から懐中電灯で照らします。
光が漏れている箇所が侵入口の可能性大です。 - 煙テスト法:室内で蚊取り線香を焚き、煙の漏れる場所をチェックします。
煙が外に出ていく箇所が隙間です。 - 紙テスト法:薄い紙を疑わしい箇所に当て、風で動くかを確認します。
紙が揺れたら、そこに隙間があります。 - 水漏れチェック法:雨の日に屋根裏や壁をチェックします。
湿っている箇所があれば、そこから水が入っている可能性があります。 - 熱画像カメラ活用法:専門業者に依頼して熱画像カメラで外壁をチェック。
温度差がある箇所が隙間の可能性があります。
特におすすめなのは、光漏れチェック法です。
夜に外から家を観察すると、昼間では気づかなかった隙間が光って見えるんです。
まるで、家が「ここから入れますよ?」とハクビシンに教えているみたいですね。
また、煙テスト法も効果的です。
煙の動きを見ることで、目に見えない空気の流れがわかります。
「ふわ?っ」と煙が外に漏れていく様子は、まるでハクビシンの通り道を示しているようです。
これらの方法を組み合わせることで、より確実に隙間を発見できます。
「でも、全部やるのは大変そう…」そう思った方、安心してください。
まずは1つか2つの方法から始めてみましょう。
隙間を見つけたら、すぐに対策を講じることが大切です。
「明日でいいや」なんて後回しにしていると、その隙にハクビシンが忍び込んでくるかもしれません。
早めの行動が、被害を防ぐ鍵となるんです。
隙間対策は「早めの実施」がカギ!後悔しない方法
ハクビシン対策で最も重要なのは、早めの実施です。「まあ、いつかやればいいか」なんて後回しにしていると、取り返しのつかない事態に陥る可能性があるんです。
なぜ早めの対策が大切なのでしょうか?
理由は主に3つあります。
- 被害の拡大を防げる
- 対策にかかる費用を抑えられる
- 心の安らぎを得られる
ハクビシンは一度侵入ルートを見つけると、そこを何度も利用します。
つまり、小さな隙間を放置しておくと、どんどん被害が大きくなっていくんです。
「最初は天井裏の音だけだったのに、気づいたら家中が糞尿だらけ…」なんてことにもなりかねません。
次に、費用面での利点があります。
小さな隙間を塞ぐ程度なら、数千円で済むかもしれません。
でも、ハクビシンが住み着いてしまった後の駆除や修理となると、数十万円かかることも珍しくありません。
「えっ、そんなにかかるの!?」と驚くかもしれませんが、本当なんです。
そして、何より大切なのが心の安らぎです。
「夜中に天井から物音がしたらどうしよう…」「子供やペットに病気がうつったら…」そんな不安とストレスから解放されるんです。
安心して眠れる夜を取り戻せるなんて、素晴らしいと思いませんか?
では、具体的にどんな対策を講じればいいのでしょうか?
ここでは、誰でも簡単にできる3つの方法をご紹介します。
- 目視点検の習慣化:週に1回、家の周りを歩いて隙間をチェック
- 季節の変わり目での重点確認:特に春と秋に入念なチェックを実施
- 簡易補修キットの常備:小さな隙間をすぐに塞げるよう準備
早めの対策で、ハクビシンのいない安心な暮らしを手に入れましょう。
家族の笑顔のために、今すぐ行動を起こすことが大切です。
効果的な隙間封鎖の方法と材料選び
金属メッシュvs発泡ウレタン「耐久性の差」に注目
ハクビシン対策の隙間封鎖には、金属メッシュと発泡ウレタンが特におすすめです。でも、それぞれに特徴があるんです。
「どっちを選べばいいの?」と迷っちゃいますよね。
まずは金属メッシュから見ていきましょう。
金属メッシュの最大の強みは耐久性です。
ハクビシンの鋭い歯や爪にも負けません。
「ガリガリ」と噛まれても、「ガシガシ」と引っ掻かれても、びくともしないんです。
一方、発泡ウレタンは柔軟性が魅力です。
複雑な形の隙間にもスッポリはまり込んで、ピッタリと隙間を埋めてくれます。
「ムニュムニュ」っと変形して、どんな隙間にも対応できるんです。
では、耐久性を比べてみましょう。
- 金属メッシュ:5?10年以上持続
- 発泡ウレタン:3?5年程度で劣化の可能性あり
実は、紫外線や雨風にさらされると劣化しやすいんです。
でも、発泡ウレタンにも良いところがあります。
施工が簡単なんです。
「シュー」っと吹き付けるだけで、隙間にぴったりフィット。
DIY初心者でも扱いやすいんです。
対して金属メッシュは、加工や取り付けに少し手間がかかります。
「ちょっと難しそう…」と尻込みしちゃう方もいるかもしれません。
結局のところ、どちらを選ぶべきなのでしょうか?
正解は、両方使うことです。
金属メッシュで頑丈に塞いで、その周りを発泡ウレタンで埋める。
これが最強の組み合わせなんです。
「なるほど!二重の防御だね」そうなんです。
これなら、ハクビシンもお手上げ。
安心して眠れる夜が戻ってきますよ。
プロ顔負けの「DIY封鎖テクニック」を伝授
さあ、いよいよDIYで隙間封鎖に挑戦です!「えっ、私にできるの?」なんて心配しなくても大丈夫。
コツさえ掴めば、誰でも上手にできるんです。
まずは、基本の手順を覚えましょう。
- 隙間の清掃:ゴミやホコリを取り除きます
- サイズ測定:隙間の大きさを正確に計ります
- 材料選び:隙間の大きさに合わせて選びます
- 材料の加工:必要なサイズにカットします
- 隙間への充填:しっかりと押し込みます
- 仕上げ:周囲をコーキングで密閉します
でも、ここからが本当の腕の見せどころです。
プロ顔負けの技を身につけましょう。
例えば、大きな隙間の封鎖。
ここでおすすめなのが「二段階封鎖法」です。
まず金属プレートで大まかに塞ぎ、その周りをシリコンコーキングで埋めます。
「ガッチリ」と頑丈な防御壁の完成です。
また、複雑な形の隙間には「型取り充填法」が効果的。
粘土で隙間の型を取り、それを元に発泡ウレタンを成形します。
「ぴったりフィット」の仕上がりになりますよ。
隙間が見つかりにくい場所には「煙テスト法」を活用しましょう。
室内で煙を発生させ、煙が漏れる箇所を探します。
「モクモク」と煙が出ていく場所が、隙間の目印になります。
封鎖後の確認も忘れずに。
「薄紙チェック法」がおすすめです。
封鎖箇所に薄い紙を当て、風で動くかを確認。
「ヒラヒラ」と動けば、まだ隙間が残っている証拠です。
「へえ?、こんな方法があったんだ!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
これらのテクニックを使えば、プロ顔負けの仕上がりも夢じゃありません。
さあ、道具を手に取って、DIY封鎖に挑戦してみましょう。
きっと、あなたの家は「ハクビシン撃退要塞」に生まれ変わりますよ。
がんばってくださいね!
季節による「建材の膨張収縮」を見逃すな!
ハクビシン対策の隙間封鎖、実は季節によって変化するんです。「えっ、季節で変わるの?」と思った方、要注意です!
建材は温度によって膨張したり収縮したりするんです。
まず、夏の暑さ対策から見ていきましょう。
暑くなると建材が膨張します。
特に気をつけたいのが屋根裏や外壁です。
「ムクムク」と膨らんで、思わぬ隙間ができちゃうんです。
- 屋根裏:熱がこもりやすく、木材が膨張
- 外壁:日光を浴びて、建材が伸びる
- 窓枠:熱で歪みが生じやすい
でも、冬も油断大敵です。
寒くなると今度は収縮が問題になります。
特に注意が必要なのが窓枠や戸袋周り。
「キュッ」と縮んで、隙間ができやすくなるんです。
- 窓枠:寒さで縮み、隙間が広がる
- 戸袋:木材が乾燥して、隙間が生じる
- 外壁:建材同士の接合部に隙間ができやすい
でも、大丈夫。
対策はあるんです。
まず、定期的な点検が大切です。
季節の変わり目には必ずチェック。
「ここに隙間ができてる!」なんて発見があるかもしれません。
次に、柔軟性のある材料を使うのがポイント。
例えば、シリコンコーキング。
温度変化に強く、膨張収縮にもついていけるんです。
また、通気性を確保するのも重要です。
適度な換気で、建材の膨張収縮を最小限に抑えられます。
「風通しがいいと、建材も長持ち」なんです。
季節の変化を味方につけることも。
春と秋の穏やかな時期に隙間チェック。
「今のうちに対策しておこう」という心がけが大切です。
こうして季節の変化に備えれば、一年中ハクビシンの侵入を防げます。
「よし、季節ごとの対策をしっかりやろう!」その意気込みが、安心な暮らしにつながるんです。
「臭いで撃退」香り付き封鎖材の意外な効果
隙間を物理的に塞ぐだけじゃない!香りを使った新しい対策方法があるんです。
「えっ、匂いでハクビシンを追い払えるの?」そう、実はハクビシンって、特定の香りが苦手なんです。
まず、ハクビシンが嫌う香りを知っておきましょう。
- 柑橘系の香り:レモンやオレンジの爽やかな香り
- ハッカの香り:清涼感のある強い香り
- 木酢液の香り:煙たい独特の香り
- ナフタリンの香り:防虫剤特有の香り
- アンモニア臭:刺激的な強い臭い
これらの香りを上手に使えば、隙間封鎖の効果がグンと上がるんです。
例えば、柑橘系オイル入り封鎖材。
発泡ウレタンにレモンオイルを混ぜて使います。
「シュー」っと吹き付けるだけで、隙間を塞ぎながら香りでも撃退。
一石二鳥の効果があるんです。
また、ハッカ油スプレーも効果的。
封鎖した隙間の周りに吹き付けます。
「スッ」とした強い香りが、ハクビシンを寄せ付けません。
木酢液を使った防腐・防虫スプレーも人気です。
封鎖材の耐久性を高めながら、ハクビシン対策もできちゃいます。
「なるほど、一石二鳥だね!」
ただし、注意点もあります。
強すぎる香りは、人間にも刺激になることも。
「うっ、鼻が痛い」なんてことにならないよう、適度な使用を心がけましょう。
また、雨や風で香りが薄れていくので、定期的な補充が必要です。
「あれ?香りが弱くなってきたかも」と感じたら、すぐに追加しましょう。
香り付き封鎖材を使えば、目に見えない防御壁ができあがります。
「ハクビシンよ、この香りの壁を越えられるかな?」なんて、ちょっと楽しくなってきませんか?
物理的な封鎖と香りによる撃退、両方の力でハクビシンをシャットアウト。
安心して暮らせる我が家の完成です。
さあ、あなたも挑戦してみませんか?
ハクビシン対策の革新的アイデアと継続的な予防法
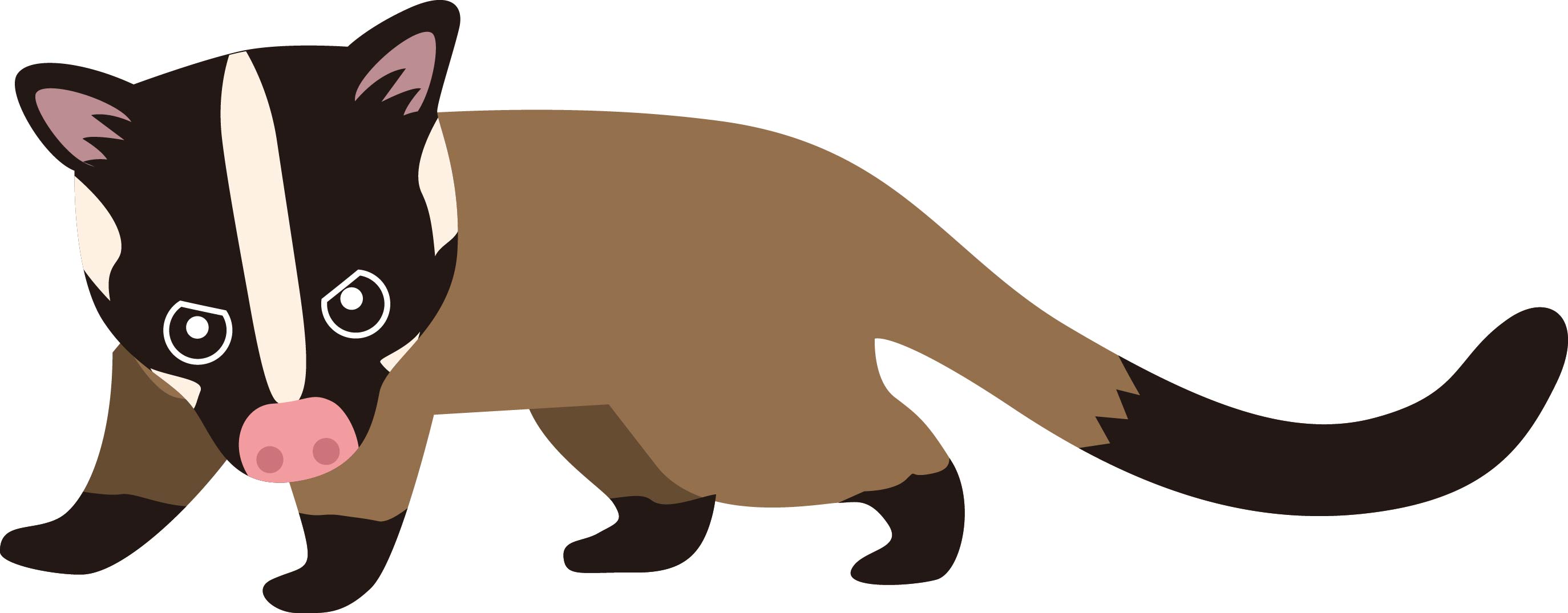
古いCDが「ハクビシン撃退の救世主」に変身!
古いCDがハクビシン対策の強い味方になるんです!「えっ、本当?」と思われるかもしれませんが、実はこれ、とっても効果的なんですよ。
CDの光沢面が反射する光は、ハクビシンにとって不快なんです。
まるでキラキラした目玉が光っているみたいで、ハクビシンはビビっちゃうんです。
「怖い!近づきたくない!」って感じでしょうか。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- CDを細かく砕きます(2cm四方くらいの大きさ)
- 砕いたCDの破片を隙間や侵入口の周りに散りばめます
- 風で飛ばされないよう、軽く接着剤で固定します
- 定期的に角度を変えて、反射の向きを調整します
でも、ここがポイント。
設置する場所や角度によって効果が変わってくるんです。
例えば、屋根裏の換気口付近に設置する場合。
月明かりが当たる向きに調整すると、夜間も効果を発揮します。
「月の光を味方につけるなんて、なるほど!」
また、庭の侵入経路には、風で揺れるようにCDの破片を吊るすのもおすすめ。
「キラキラ」と不規則に動く光が、ハクビシンを混乱させるんです。
ただし、注意点もあります。
人の目にも眩しいので、窓の近くには設置しないようにしましょう。
「目が痛くなっちゃった」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
この方法、コストもかからないし、環境にも優しい。
まさに一石二鳥のアイデアです。
「よーし、早速やってみよう!」そんな気持ちになりましたか?
古いCDに新しい使命を与えて、ハクビシン撃退に挑戦してみてください。
猫砂の意外な使い方「ハクビシン寄せ付けない秘策」
猫砂がハクビシン対策に大活躍!「えっ、猫砂?」と驚かれるかもしれませんが、これが意外と効果的なんです。
実は、ハクビシンは猫を天敵と認識しているんです。
だから、猫の匂いがするところには近づきたがりません。
「なるほど、猫の匂いを利用するわけだ!」そうなんです。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- 使用済みの猫砂を用意します(新品よりも効果的)
- 小さな布袋やストッキングに猫砂を入れます
- ハクビシンの侵入経路や隙間の周りに配置します
- 2週間ごとに新しいものと交換します
まず、配置する場所。
ハクビシンの通り道を想像して、そこに重点的に置きましょう。
例えば、屋根裏への侵入口や、庭の柵の周りなどです。
「ハクビシンの気持ちになって考えるんだね」
また、雨に濡れないよう工夫することも大切。
「せっかくの効果が水の泡にならないように」ですね。
軒下や屋根のある場所を選びましょう。
ただし、注意点もあります。
猫を飼っていない家庭では、近所の猫が寄ってくる可能性も。
「困ったことに猫が集まってきちゃった!」なんてことにならないよう、適度な量を守りましょう。
この方法、コストも低く、簡単に始められるのが魅力です。
「よし、さっそくやってみよう!」そんな気持ちになりましたか?
ハクビシン対策と猫砂のリサイクル、一石二鳥ですよ。
自然の力を借りた、エコでスマートな対策。
試してみる価値は十分にあります。
さあ、あなたも猫砂パワーでハクビシンを撃退しましょう!
風鈴の音で「ハクビシンを警戒させる」新発想
風鈴の音色がハクビシン撃退に一役買うんです!「えっ、風鈴?」と思われるかもしれませんが、これが意外と効果的なんですよ。
実は、ハクビシンは予期せぬ音に敏感なんです。
特に金属音は苦手。
風鈴のチリンチリンという音が、ハクビシンにとっては「危険信号」になるんです。
「なるほど、音で警戒させるわけか!」
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- 金属製の風鈴を選びます(音が澄んでよく通るため)
- ハクビシンの侵入経路付近に設置します
- 風がよく通る場所を選びます
- 複数の風鈴を異なる高さに配置します
まず、設置場所。
ハクビシンの通り道を想像して、そこに重点的に配置しましょう。
例えば、屋根裏への侵入口や、庭の柵の周りなどです。
「ハクビシンの気持ちになって考えるんだね」
また、風鈴の音色にも注目。
低音から高音まで、様々な音を組み合わせるのがポイント。
「いろんな音で攻めるってわけだ!」そうなんです。
ハクビシンを混乱させる効果が期待できます。
ただし、注意点もあります。
近所迷惑にならないよう、音量には気をつけましょう。
「夜中にジャラジャラうるさい!」なんて苦情が来ちゃったら大変です。
この方法、見た目も楽しめて一石二鳥。
「風鈴の音色を楽しみながらハクビシン対策できるなんて素敵!」そんな風に思ってもらえたら嬉しいです。
季節を感じる風鈴の音色。
それがハクビシン対策にもなるなんて、なんだかポエティックですよね。
さあ、あなたも風鈴の音色でハクビシンを撃退しましょう。
きっと、心地よい夏の風情も楽しめますよ。
柑橘系の香りで「自然派ハクビシン対策」を実現
柑橘系の香りでハクビシンを撃退できるんです!「えっ、そんな簡単なことで?」と驚かれるかもしれませんが、これが結構効果的なんですよ。
実は、ハクビシンは柑橘系の強い香りが苦手なんです。
レモンやオレンジの爽やかな香りが、ハクビシンにとっては「近寄りがたい」匂いなんです。
「なるほど、香りで防御するってわけか!」
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- レモンやオレンジの皮を乾燥させます
- 乾燥させた皮を小さな布袋に入れます
- ハクビシンの侵入経路付近に配置します
- 2週間ごとに新しいものと交換します
まず、皮の乾燥方法。
天日干しがおすすめです。
「太陽の力で香りを凝縮するんだね」そうなんです。
香りが強くなって、効果も長持ちします。
また、配置する場所も重要。
ハクビシンの通り道を想像して、そこに重点的に置きましょう。
例えば、屋根裏への侵入口や、庭の柵の周りなどです。
「ハクビシンの気持ちになって考えるんだね」
ただし、注意点もあります。
雨に濡れると効果が薄れるので、屋根のある場所に置くのがポイント。
「せっかくの香りが雨で流れちゃう」なんてもったいないですからね。
この方法、環境にも優しくて安心。
「化学物質を使わないから、子供やペットにも安全だね」そうなんです。
自然の力を借りた、エコでヘルシーな対策なんです。
柑橘系の爽やかな香り。
それがハクビシン対策にもなるなんて、なんだか素敵ですよね。
「家中が良い香りになりそう!」そんな楽しみも加わって、一石二鳥です。
さあ、あなたも柑橘系の香りでハクビシンを撃退しましょう。
きっと、爽やかな香りに包まれた快適な暮らしが待っていますよ。
定期点検で「再侵入リスク」を最小限に抑える方法
定期点検こそがハクビシン対策の要!「えっ、そんな当たり前のこと?」と思われるかもしれませんが、これが実は一番大切なんです。
なぜなら、ハクビシンは一度侵入に成功した場所を覚えているんです。
そして、新たな隙間を見つけては再侵入を図ろうとします。
「なるほど、油断大敵ってわけだ!」
では、効果的な定期点検の方法を見ていきましょう。
- 月に1回、家の外周をくまなくチェックします
- 特に屋根裏、軒下、換気口を重点的に確認します
- 新たな隙間や破損がないか細かくチェックします
- 見つけた問題はすぐに対処します
- 季節の変わり目には特に注意して点検します
まず、チェックリストを作りましょう。
「忘れずに全部確認できるんだね」そうなんです。
漏れがなくなり、効率的に点検できます。
また、写真を撮って記録するのも有効です。
「前回との違いがわかりやすくなるんだ!」その通り。
小さな変化も見逃さず、早期発見・早期対応ができます。
ただし、注意点もあります。
高所の点検は危険が伴うので、無理はせず、必要に応じて専門家に相談しましょう。
「安全第一が一番大切だもんね」
この定期点検、面倒くさく感じるかもしれません。
でも、「予防は治療に勝る」ということわざがあるように、先手を打つことが実は一番の近道なんです。
「よし、これからは定期点検をしっかりやろう!」そんな気持ちになりましたか?
定期点検を習慣化することで、ハクビシン対策はぐっとレベルアップします。
安心して暮らせる我が家を守るため、定期点検をしっかり行いましょう。
きっと、あなたの家はハクビシンにとって「入りにくい家」になるはずです。
頑張ってくださいね!